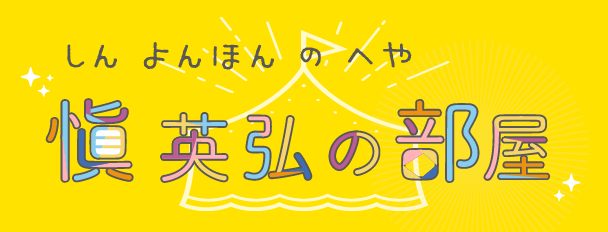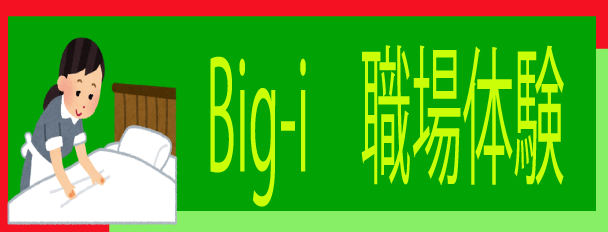国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)
国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)は、障がいのある方も、ない方も、
すべての人にご利用いただける施設です。障がい者が主役の芸術・文化・国際交流活動の機会を創出し、
障がい者の社会参加促進をめざします。施設内には、多目的ホールや研修室、宿泊室、レストランを備えています。
News
お知らせ
愼英弘の部屋VOL.13『自立』についての旧態依然たる意識
2025.07.03
愼英弘の部屋
障害者の自立や社会参加に対する市民の意識調査がときどき行われている。それによると、障害者理解は徐々に進んできているといえる。たとえば、道や駅ホームで障害者に手助けの声かけをする人が多くなっている。
しかし、その一方で、自分自身に直接関係するような場面においては、障害者の受入れを拒否することがいまだに多く見受けられる。2025年1月から2月にかけて実施された盲導犬使用者を対象にしたアンケート調査の結果からもそれは明らかである。それによると、2024年の1年間で、盲導犬と同伴での受入れを拒否された経験があると回答したのは約48%であった。たとえば、飲食店への入店を拒否されたケースは約43%であり、交通機関の利用を断られたのは約14%であった(詳しくは『点字毎日』2025年5月13日付、4~5頁を参照されたい)。このような状況について、「2020年の調査時の約52%と比べるとほぼ横ばい。身体障害者補助犬法施行から20年以上経ち、合理的配慮の提供を義務化する障害者差別解消法が昨年[2024年-引用者]改正されても、なお施設利用を断られる現状が浮かんだ。また、法改正で人々の理解が変化したとは思わないとの回答が約77%に上った」(前掲、4頁、傍点引用者)と報じている。
盲導犬の使用は、自立した日常生活や社会生活を送るための視覚障害者の生活の一つのあり方である。それにもかかわらず、飲食店等の施設の関係者の中には、視覚障害者の自立した日常生活や社会生活を阻む意識にまみれている者がいるのである。
この77%の回答は盲導犬使用者の立場からの意識である。それでは、いわゆる健常者をはじめとする社会の人々は、障害者の自立についてどのような意識をもっているのだろうか。とはいえ、ここでは、意識調査をするのではなく、一つの事象を手がかりに考えることにする。
今回は、「障害者の自立」ということについて、「根強い後ろ向きの見方」がある事例を取り上げて述べることにする。
「『自立』についての旧態依然たる意識」
1.私の愛読する『点字毎日』
毎日新聞社が100年以上にわたって発行し続けている点字の週刊新聞がある。その名称は『点字毎日』。私は、それを1985年から購読している。
『点字毎日』には一般的なニュースも掲載されているが、視覚障害者に関連する記事が多くあり、視覚障害者が執筆したエッセイや料理のレシピなど多岐にわたっている。視覚障害者に関連する記事には、私の研究に直接関係のある興味深いものもある。年金問題や障害者政策等に関する学術論文を作成する際に引用させてもらっている。
『点字毎日』に毎回掲載されているものに「近望遠聞」という欄がある。『点字毎日』の記者が毎週交代で執筆している。記者の人となりを知ることができるので、毎週楽しんで読んでいる。そこで取り上げられていた内容が、今回の話の中心である。
2.試験問題に出すとは
2025年4月15日付の『点字毎日』の「近望遠聞」に驚く内容が書かれていた。それは記者・谷本仁美さんのお子さんが受験したある私立中学校の模擬試験の問いの内容とその正答例についてである。その部分を引用する。
「社会科の問題文で、視覚障害者を支えるものとして、点字ブロックやホームドア、駅のホームにある『あなたの一声が目の見えない人の命を救います』というポスターを挙げていた。一方で、『ある観点から、視覚障害者の方を切符売り場などへ誘導することは避けた方がよい場合もあるという考え方もあります』と続け、どのような観点から避けた方がいいのか、という問いだった。」(傍点引用者)
私は、「ある観点から」とはどのような「観点か」をいろいろ考えてみた。ICカードか回数券を持っているかもしれないので、切符売り場への誘導は必要ないのではないか、などと考えてみたが、どうもすっきりしない。「ある観点から」というのであるから、おそらくものの見方を答えさせようとしているのだろうと思ったが、私には答えらしきものを導き出すことはできなかった。
同「近望遠聞」によると、正答例は、「視覚障害者の方がなるべく自立した生活を送ることを促すという観点」とのことだそうである。
なんという正答例! 支援と自立の関係をわきまえていない正答例! 旧態依然たる意識が背景にあることを強調しているとしか思われない短絡的な考え方に基づく出題であり、正答例だと断じざるを得ない。
次項で述べるように、障害者を支援(手助け)することによって、その人の自立を妨げることになる、という考え方をもっている人が一部いることを否定はしない。そのような人がいるからといって、支援が自立を阻害することがあるとの後ろ向きの考え方を強調するかのような試験問題を作成して、それを模擬試験に出すことが、果たして教育的立場に立った試験問題であるといえるのだろうか。
3.勤務していた当時の経験
私が大学に勤務していたときに視覚障害者(全盲)が入学してきた。すぐに数人の学生が支援のために集まってきた。ところがしばらくすると、一人を残してほかの学生はその視覚障害学生から離れていった。その理由はまさにこの試験の「正答例」とされている「観点から」である。
つまり、学生たち曰く「卒業したら社会に出る。社会では支援する人が見つかるとは限らない。だから、支援者がいなくても一人でできるようになってもらうために自分たちは離れていく」と。この学生たちの本音がどこにあるのかは判らないが「正答例」なるものと相通ずるところがある。それは「自立するには人の手を借りるべきではない」「手助けをするとその人の自立を阻害する」「いわゆるある観点なるものが正しいと思い込んでいる」等々である。
いわゆる健常者にはできても障害者にはできないことやできにくいことがあるのは否定しようがない。すなわち障害者はさまざまな特別な困難を抱えている。その特別な困難を解消するにはいろいろな方法があるが、その一つに周辺の人からの支援(手助け)がある。支援は自立を阻害するものではなく自立のためには欠かすことができない重要なものである。谷本さんの「同行援護も否定するの?」との批判的な指摘はまったくその通りである。
「同行援護」とは、視覚に障害がある者が外出したときに、安全を確保しながら移動したり、情報提供したり、代読・代筆したり、トイレ等の介護をしたりする支援のための福祉サービスである。この福祉サービスは、視覚障害者が自力ではできないことやできにくいことを手助けする制度である。このサービスを受けることによって、視覚障害者は自立した日常生活や社会生活を送ることができるのであって、決して自立を阻害するようなものではない。
前述した視覚障害学生の支援を何人かの学生は続けた。その支援と本人の努力によって、卒業式を迎えることができた。その視覚障害学生は卒業生を代表して答辞を読んだ。その中で、「学生生活の4年間に親しい友人ができ、その友人は私の生涯の宝です!」との内容を切々と訴えた。その答辞を聴いていた私は思わず涙がこぼれそうになり、涙をこらえるのに必死になった。理事長や学長は涙を流していたとのことである。それほどに、学生生活を支えてくれた友人学生への強い想いが伝わった答辞である。
4.自立と自立支援
赤ちゃんを授かった親の思いを表した言葉がある。「這えば立て、立てば歩めの親心」。その子が成長するにつれて、「自立」ということが強調されていく。自分の身の回りのことは自分一人でできるようになってほしい。学齢になると、親から言われなくても予習や復習の勉強をするようになってほしい。学校を卒業したら働いて自活してほしい。等々。親の思いは尽きることがない。すなわち、ひとことで言ってしまうと、親は子どもに対して自立を期待するのである。
このときの親の思いの「自立」は、何もかも自分一人でできるようになることを念頭においているのだろう。しかし、障害者の場合には、自力ではできないことやできにくいことがあるのは否定しようがない。したがって、障害者が健常者同様の生活をするためには、自力ではできないことやできにくいことについては手助けを受ける、すなわち支援を受ける必要がある。その手助け(支援)を受けることによって、障害者は健常者同様の日常生活や社会生活を送ることができるようになるのである。
障害を受けた時期や障害の程度によって、その障害者が必要としている支援(手助け)は異なってくるのは改めていうまでもないだろう。「十人十色」という言葉があるように、障害者が10人寄れば、必要としている支援(手助け)は異なってくる。しかし、行政の施策による福祉サービスは、一人一人の必要性に応じて提供するのはなかなか難しいので、一定の基準に基づいたサービスになってしまっている。
ところが、制度に依らない支援(手助け)は、障害者一人一人に対して、その障害者が必要としている支援(手助け)をすることが可能である。それは、障害者に声かけをして、どんな支援(手助け)が必要かを尋ねたらいいのである。支援(手助け)の声かけがあったとき、障害者が自分一人でできると判断した際には、「大丈夫です」とか「一人でできます」とか答えるはずである。したがって、前述の試験問題の「正答例」なる「視覚障害者の方がなるべく自立した生活を送ることを促すという観点」は、障害者に声かけをして、その意志を確かめるという重要な前提を無視した結果から導き出された「正答例」にすぎないといわざるを得ないのである。
Contact
お問合せ
障がい者の文化芸術活動及び鑑賞に関するご相談・
事業・ホームページ・情報紙に関するお問合せ
072-290-0962
受付時間:平日 10:00~18:00