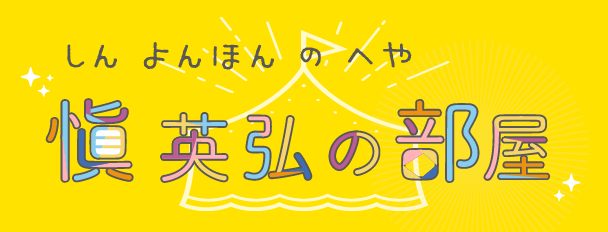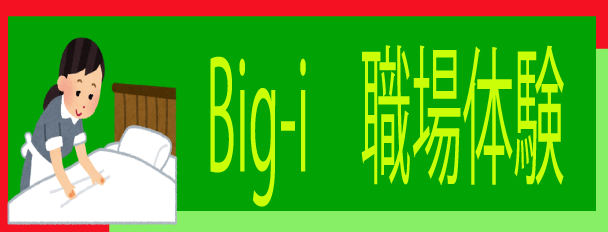国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)
国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)は、障がいのある方も、ない方も、
すべての人にご利用いただける施設です。障がい者が主役の芸術・文化・国際交流活動の機会を創出し、
障がい者の社会参加促進をめざします。施設内には、多目的ホールや研修室、宿泊室、レストランを備えています。
News
お知らせ
愼英弘の部屋VOL.14「視覚障害者の単独歩行」
2025.07.08
愼英弘の部屋
全盲の視覚障害者にとって、単独での移動にはさまざまな危険が立ちはだかっている。また、最近、大きな社会問題になっている鉄道の「無人駅化」は、視覚障害者にとって危険状態を回避することが困難になるだけではなく、ICカードにトラブルが生じたときには改札口から出ることができなくなることもあるなど、さまざまな問題を生ぜしめるおそれがある。
今回は、視覚障害者の鉄道利用や、歩行環境の問題について単独歩行をしている私が経験したことや、日頃から考えていること等について述べることにする。
「視覚障害者の単独歩行」
本題に入る前に、視覚障害者やその関係者の間では日常的に使用されている言葉について説明しておく。
単独歩行:視覚障害者が晴眼者(目の見える人のこと)の手を借りずに、一人で町中を移動すること。周辺の状況を確認したり、視覚障害者であることを周辺の人に知らせたりするために、一般的には白杖を携えたり盲導犬を連れたりして歩く。
一人歩き:単独歩行のこと。独り歩きとも書く。
歩行環境:視覚障害者が単独歩行(一人歩き)する際に、安全に歩くために手がかりになるような点字ブロック等の物理的なものや音等の環境(状況)のこと。
移動環境:視覚障害者が移動する際の交通機関や建物の構造、道路の状況、人の混雑ぶり等の移動時の周辺の環境(状況)のこと。
「歩行環境」と「移動環境」を同義として使用する者もいるが、ここでは上記のように異なる意味をもつ用語として使用する。
1.移動の自由を妨げるもの
一般的にいって、多くの人は買い物や映画に行ったり、町中を行きたいところに行ったりするのは、特別な場合を除いては自由である。特別な場合というのは、事故が起きるおそれのある「禁止区域」や、特定の条件の人しか入場できない建物に入ったりする場合である。「多くの人」の中には障害者が含まれていることもあるが、現実には、障害者は自由に移動することが困難な場合がある。それは、物理的な障壁があったり、社会の人々の理解がなかったりすることによる。
視覚障害者の「移動の自由」は法令や制度によって禁止されてはいない。しかし、視覚障害者とりわけ全盲者は町中を「自由に移動する」ことが困難な状況におかれている。視覚障害者の「移動の自由」を阻害する要因として、少なくとも次の4点を挙げることができる。
(1)家族等の無理解:
視覚障害者とりわけ全盲者の親や兄弟姉妹の中には、視覚障害者が単独で外出することに理解のない者がいる。それは、一人での外出時に視覚障害者が事故に遭って怪我をしたりすることを心配してのことである。それは無理からぬことではあるが、視覚障害者にとっては、単独での外出を禁じられることによる精神的苦痛や孤独感は筆舌に尽くしがたいものがある。
私は一時期、親戚の者と同居していたことがある。私は自宅から駅まで、白杖1本を頼りに単独で行くことはできた。しかし、その親戚の者は、常に私を駅まで送ってくれた。その理由は、もちろんのこと怪我をしないようにとの心配りからである。しかし、ときどき「目が見えない者が一人で歩くのは他人に迷惑をかける」と強く言われた。
このような家族等の心配りには感謝をしているが、この「心配り」は視覚障害者の単独歩行、言い換えるならば、視覚障害者の自立した日常生活や社会生活を阻害するものになっているという事実もあることを看過してはならない。したがって、家族等の無理解を、いかにして解決するかは大きな課題である。
私は外出しようとするときに、どんなに体調が悪くても、土砂降りの雨が降っていても、駅まで家族に送ってもらうことはない。なぜなら、人に頼れば安心して歩く=移動することはできるが、単独で歩行する勇気を押しつぶしかねないからである。念の為に一言しておくが、私自身は単独での歩行をする勇気をいつももっていたいのであって、周辺の人からの手助けや同行援護制度等のガイドヘルパーの支援を否定しているのではない。それが証拠に、知らないところに行ったり、遠くでの会議に行ったりするときには、同行援護制度による外出の支援を受けている。
(2)一部の社会の人々の言動:
私は休日を除いてほぼ毎日のように外出している。1週のうち3日は図書館に通い、1日は仕事に出かけ、ときどきは会議に行ったりカラオケボックスに行ったりしている。いずれの場合も、目的のところまでは単独歩行で出かけている。このように、遠出以外は単独歩行による。
単独での外出をしていて、いやな思いをすることがしばしばある。それは、すれ違う人から投げかけられる言葉である。「目の見えない者は一人で歩くな!」「何でぶつかるんや!」「目の見えない者は家から出るな!」等々である。それも差別語を使ってである。私はそんな言葉にくじかれるようなことはないが、視覚障害者の中には、そのような言葉によって傷つけられる者もいるだろう。場合によっては、単独歩行をやめようと思う者もいるかもしれない。
このような嫌がらせともいえる言葉を投げかける人の気持ちを推し量りたくもないが、言われた視覚障害者の気持ちがいかばかりかは想像に難くない。
このような言動をとる人がないようにするには、視覚障害者に対する理解を求めるための啓発や、人権尊重の意識を培うための啓発や教育の充実が必要である。このような問題を解決するのも大きな課題である。
(3)道路や駅ホーム等にある物理的障壁:
「犬も歩けば棒に当たる」という言葉があるが、視覚障害者とりわけ全盲者が道路(道)を歩けば、ごみ箱や止めてある自転車、店先から出ている商品や看板、等々にぶつかることがたいへん多い。そのようなものにぶつかった経験のある視覚障害者は私だけではない。ほとんどの視覚障害者が経験しているといえる。
あるとき、店先に止めてあった自転車に私はぶつかり、その自転車は倒れた。その自転車には買い物をした品物が積んであったようで、パックに入っていた卵の何個かが割れたと言われた。仕方がないので、その割れた卵の代金を弁償した。弁償するような経験は滅多にないが、それにしても道にあるものにはよくぶつかる。特に自転車にぶつかると、その自転車の金具にズボンを引っかけて破れることがときどきある。大きく破れたときには、補修がきかないために、スーツそのものを捨てざるを得なかったことが3回もあった。
私が経験したことではないが、新聞の報道によると、券売機のところで切符を買おうとしていた人に、盲導犬を連れた視覚障害者がぶつかってきて、その人は転んで骨を折ったとのことである。その骨を折った人は、賠償を求める裁判を起こした。盲導犬を連れた視覚障害者とその骨を折った人との間は2メートルほど空いていたという証言があり、賠償に応じる必要はなくなった。こんな出来事に出合う視覚障害者もいるのである。
物理的障壁は道路上だけにあるのではない。特に駅ホームではそれが目立つ。
多くの駅のホームは幅が狭い。幅が狭いところに柱や椅子があり、さらには、足元に荷物を置いた利用客が立っていたりする。それらは視覚障害者にとっては物理的障壁以外の何ものでもない。柱や椅子にぶつからないように注意をしながら視覚障害者は歩くが、たまにはそれらにぶつかって顔や足を打って怪我をすることがある。私も眉毛のところに3カ所の傷が今もある。
私の友人の視覚障害のある者が、ホームを歩いていて立っている利用客にぶつかったことがある。その利用客はぶつけられた衝撃でホームから転落した。幸い怪我をしなかったので大ごとにはならなかったが、視覚障害者自身だけではなく周りの人が怪我をしかねない状況もあるのである。
視覚障害者が一人で買い物に行ったときには、商品にぶつかって倒すこともある。高校の修学旅行に行ったとき、私はみやげを買おうとした。探していて台の上に置いてあったガラスの商品が倒れて壊れたことがあった。「すみません。弁償します」と言うと、その店の人は「かまいません」と言ってくれた。とてもありがたかったが、申し訳なくて、あれから58年も過ぎ去った今も記憶に鮮明に残っている。
このように、さまざまなところに物理的障壁があるために、視覚障害者が単独歩行するには危険が伴うのである。このような状況があるがゆえに、視覚障害者は「移動の自由」があるにもかかわらず、「自由に移動することが困難」なのである。
視覚障害者が単独歩行で町中を自由に移動することができるようにするには、以上述べたようなさまざまな危険な状況を回避するために、店から商品をはみ出させないようにする等の社会の人々の心がけや、物理的環境を整える安全対策が必要である。このような物理的障壁をいかにして無くすかも大きな課題である。
(4)安全対策の不充分さ:
道路を安全に横切るためには、音響式信号機の設置が欠かせないが、住宅地にはそれが少ない。設置されているとしても、朝の8時頃から夜の8時頃までは信号機から青であることを知らせる音が鳴っているが、それ以外の時間帯には音が止められているので、道路を横断するのに危険な状況がある。
危険な状況は道路を横断するときだけではない。今から50数年前のことであるが、私の盲学校時代の友人が、マンホールに落ちたことがある。それも3人もである。つまり、工事中のマンホールの蓋が開いていて、その中に落ちたのである。現在では工事現場には警備員がいて事故が発生しないように注意を払っているが、50数年前は、そのような警備員がいないことがあった。そのためにマンホールに落ちる危険な状況があったのである。
現在でもときどきは警備員が、何らかの用事で工事現場を離れていることがあるが、安全対策上そのようなことがないようにしてもらいたいものである。安全対策の不充分さは、単独歩行をする視覚障害者の移動の自由を阻害する何ものでもないことを知ってもらいたい。したがって、いかにして安全対策を充実させるかも大きな課題である。
2.移動の自由を保障するためには
町中のみならずさまざまな場所にある物理的な障壁については、充分かどうかは別として「安全対策」がとられているだろう。とはいえ、歩行中の安全確保のためには、それぞれの人が自ら注意を払っていることは改めていうまでもないだろう。
いわゆる健常者の場合には、歩行中の安全確保は、一般的には、自らの力で行っている。単独歩行をしている視覚障害者の場合も同様である。しかし、周辺状況が充分に把握し得ない視覚障害者にとっては、自らの力だけでは安全確保が困難な状況があることは否定しようがない。
視覚障害者は注意に注意を払って駅のホーム上を歩いているが、それでもホームから転落することがある。視覚障害者のホームからの転落事故をめぐって裁判が起こされたときには、検察官は「視覚障害者には過重された注意義務がある」などと断じ、ホームから転落した視覚障害者に注意義務違反があったとの立場をとっていたこともある。
このように、過重な注意義務を課せられる視覚障害者は、単独歩行での外出に際しては計り知れない緊張を強いられることになる。したがって、単独歩行によらなくても外出が可能になるような支援政策がとられている。それはガイドヘルパーの制度である。
とはいえ、ガイドヘルパー制度、現在の名称でいうならば「同行援護制度」は、1カ月に利用できる時間数に制限があり、かつ、利用に当たっては原則として事前予約が必要であり、利用料を負担しなければならない利用者もいるので、いつでも自由に利用できるというわけではない。したがって、単独歩行による外出をせざるを得ない状況があることは多言を要しない。
このような状況に置かれている視覚障害者の単独歩行での「移動の自由」を保障するためには、視覚障害者の「歩行環境」や「移動環境」に関して、少なくとも次の10点を充実させることが必要であると私は考えている。
(1)点字ブロックの統一された基準での敷設:
「点字ブロック」とは視覚障害者のための設備の名称であって、その設備に点字が記されているのではない。「ブロック」となっているが、材質はタイルであったり金属であったりゴムのようなものであったりとさまざまである。
点字ブロックは形状からして「線ブロック(線状ブロック)」と「点ブロック(点状ブロック)」との2種類がある。これらはその機能からして、前者は「誘導ブロック」ともいい、後者は「警告ブロック」ともいう。
誘導ブロックは、その名称からも判るように、そのブロックに従って歩くとどこかに誘導されるという機能を果たしている。いつも同じ誘導ブロックを利用している視覚障害者は、それがどこにつながっているかを知っているので役に立つ。しかし、初めて通る道で誘導ブロックを踏んだ視覚障害者に対して、どこに誘導するかは示していないので、必ず役に立つものとは言いがたい。いかにして誘導先を示せるようにするかは大きな課題である。
警告ブロックは、その上に立っていたり、その上を歩いていたりするのは安全だが、そのブロックからはずれると危険であるとの警告を示す機能を果たしている。しかし、その警告ブロックの上に荷物が置かれていたり人が立っていたりすることがあり、警告ブロックの上を歩いている視覚障害者がその荷物にけつまずいて転んだり、立っている人にぶつかったりすることがときどきある。警告ブロックの機能が充分に認識されるようにするのも大きな課題である。
点字ブロックにおいてこれらふたつの課題があるがゆえに、視覚障害者が町中を移動したり、駅舎を利用したりするときの点字ブロックは、安全確保上において完全なものではなく、視覚障害者の単独歩行における安全確保のための補助的手段の一つなのである。
点字ブロックの敷設において、一定の基準はあるものの、それは充分なものとは言いがたい。特に駅ホームにおける点字ブロックの敷設は、鉄道会社によって異なっていることがある。また、駅ホームの幅の広さによっても、ホームの縁端から点字ブロックまでの距離が異なっていることもある。
「内方線付き警告ブロック」というのがある。これは、ホーム上に設置されている警告ブロックのどちら側に線路があるかを判らせるために、警告ブロックの片側に線状のブロックを付けたものである。すなわち、線状のブロックが付いている警告ブロックの反対側に線路が走っていることを示すためのブロックである。この内方線付き警告ブロックがあることによって、警告ブロックのどちら側が線路であるかを視覚障害者は知ることができるのである。しかし、この内方線付き警告ブロックが、すべての駅ホームに敷設されている訳ではない。
駅ホームにおける内方線付き警告ブロックの敷設の充実を図る必要がある。(4)で述べる可動式ホーム柵の設置がすべての駅舎になされるまでの間は、この内方線付き警告ブロックの敷設は、視覚障害者のホームからの転落事故を防ぐためには重要な設備である。
<前記の点字ブロックの画像について 埼玉県ホームページ「点字ブロックは視覚障害者の命綱です」で詳しく掲載していますのでご参照下さい。 埼玉県「点字ブロックは視覚障害者の命綱です」>(外部サイト)
(2)異種鳴き交わし式の音響式信号機の設置の充実:
音響式信号機とは、信号の色が青になると信号機から音が出るようになっている信号機のことである。音は、かつては音楽であったが、現在はほとんどのところが「ピヨピヨ」や「カッコウカッコウ」という鳥の声の音である。
道路を挟んで設置されている信号機から出る音は、かつては、道路を挟んで両側の信号機の音が同時に鳴っていたが、現在では、道路を挟んだ信号機の音が交互に鳴るようにしたものが増えつつある。このような音が交互に鳴るものを「鳴き交わし式信号機」という。
道路を挟んだ二つの信号機から同時に音が出ると、十字路の場合にはどの方向に渡っていいのかが判らない状況がある。鳴き交わし式信号機だと、道路を挟んで音が交互に鳴るので、どの方向に渡ればいいかがはっきりと判るのである。したがって、同時に音が出る信号機に比べて、鳴き交わし式信号機のほうが、視覚障害者にとっては方向を間違えないなど安全確保上有用である。
とはいえ、道路幅が広かったり、出ている音が小さかったりすると、歩いている途中で音が聞こえにくくなったりすることがあるために、まっすぐに歩くのに困難を来すことがしばしばある。まっすぐに歩くことができるようにするためには、地面に「エスコートゾーン」を設ける必要がある。「エスコートゾーン」とは、点字ブロックに似た印を横断する道路上に敷設されたところである。これがあれば、たとえ道路幅が広くても、音響式信号機の音が小さくても、ほぼまっすぐに道路を横断することができるのである。しかし、エスコートゾーンが設けられているところは極めて少ない。
十字路の場合に、同じ種類の音が出る信号機だと、どの方向が青なのかが判らなくなる。そこで、音の種類を変えた信号機が設置されている。一般的には「ピヨピヨ」という音と「カッコウカッコウ」という音で区別している。京都の町は碁盤の目のように整備されているので、東西が青の場合は「カッコウカッコウ」という音であり、南北が青の場合は「ピヨピヨ」という音にしてある。大阪の場合は、町が碁盤の目のようにはなっていないので、十字路の幅の広い道は「カッコウカッコウ」という音であり、狭い道のほうは「ピヨピヨ」という音にしてある。
このように、十字路の場合に2種の異なった音の出る信号機を設置することによって、視覚障害者は渡る方向を確認することができるのである。この2種類の音がそれぞれ交互に鳴るのが「異種鳴き交わし式信号機」である。
異種鳴き交わし式の音響式信号機は、視覚障害者にとっては、渡る方向を確実に把握することができるので、安全確保上のためには最も有用であることはことさらにいうまでもないが、設置されている音響式信号機の数からすると、まだまだ少数である。したがって、視覚障害者の「移動の自由」を保障するためには、異種鳴き交わし式信号機の設置をいっそう進めるという「移動環境の充実」が課題である。
(3)エスコートゾーンの設置の充実:
エスコートゾーンとは何かについては、(2)で述べた。
繰り返して述べるが、視覚障害者が道路を安全に横断することができるようにするための設備の一つがこのエスコートゾーンである。
音響式信号機さえあれば、視覚障害者は交差点の道路を安全に渡ることができると思っている人がほとんどかも知れない。しかし、風の向きなどによって、交差点の斜め向こうの音が聞こえたりすることがある。そのために、道路を横断しようとしているにもかかわらず、交差点の中に入り込んでしまうことがある。私自身これまでに7回もそのような状況に陥ったことがある。反対側から走ってくる自動車にはねられるのではないかという恐怖は筆舌に尽くしがたい。白杖を持った者が交差点の中で立ち往生しているのを見ても、自動車はスピードを落とすこともなく横を走り抜けて行く。
道路上には「横断歩道」の印があるように、横断歩道と同様の意味合いでエスコートゾーンを設置するならば、視覚障害者は道路を横断するに際して斜めに横断したり曲がりくねって横断したり交差点の中に入り込んだりすることがないようになる。エスコートゾーンの充実は、まさに視覚障害者の「移動環境」と「歩行環境」の充実なのである。
(4)駅ホームからの転落を防止するための可動式ホーム柵等の設置の充実:
「可動式ホーム柵」とは、駅ホームの線路側に柵を設置し、電車が到着したときに、電車のドアの部分に当たるその柵の一部が開くようになっているホーム柵のことである。これは、鉄道の利用客がホームから転落しないようにするための「転落防止柵」である。
「ホームドア」というものもある。これは、駅ホームの線路側が壁のようになっており、電車が到着すると、電車のドアの部分に当たるその壁の一部が開くようになっているものである。これも、利用客が駅ホームから転落しないようにするための設備である。
可動式ホーム柵やホームドアは、駅ホームからの転落を防止するための視覚障害者だけを対象にした設備ではない。昨今は、電車に接触したり駅ホームから転落したりする利用客が増えており、そのような事故を防ぐために設置が進んでいる安全対策の設備なのである。
可動式ホーム柵は、視覚障害者の駅ホームからの転落を防止するための設備としては最も有用であることは多言を要しない。したがって、視覚障害者や視覚障害者団体は、可動式ホーム柵の設置を要望し続けてきた。しかし、なかなかその設置は進まなかった。前述したように、駅利用客の電車との接触事故や駅ホームからの転落事故が多発するようになり、鉄道会社も本格的にその設置を進めざるを得ない状況になったのである。
東海道新幹線が開通したとき、熱海駅には可動式ホーム柵が設置された。ほかの新幹線駅にも設置すべきであるのに、なぜ熱海駅だけだったのかの理由は判らないが、現在では新幹線の駅ホームにもこの可動式ホーム柵が増えつつある。たいへん良き状況である。
私鉄における可動式ホーム柵の設置は非常に遅れている。というよりも、設置はほとんど進んでいないといったほうがよい状況である。JRの在来線の駅ホームも可動式ホーム柵が増えつつあるとはいえ、すべての駅ホームに可動式ホーム柵が設置されるには、まだまだ長い時日を要することは否めない。したがって、可動式ホーム柵がすべての駅ホームに設置されるまでの間は、視覚障害者の駅ホームからの転落を防止するためには他の安全対策が必要である。その第一は、駅ホームに必ず駅の係員を配置することである。
(5)鉄道の駅における駅係員による利用者への声かけと誘導の充実:
駅ホームからの転落を防止するための可動式ホーム柵が設置されていなくても、必ず駅の係員がホーム上に配置されているならば、転落を防止することは可能である。「可能」としたのは、駅係員がホーム上にいたとしても、おそらく200メートル以上もあるような長いホームの端にいたならば、利用客がホームから転落しかけたのに気づいて駆けつけようとしても間に合わないかも知れないからである。
とはいえ、白杖を持った利用客が階段やエスカレーターやエレベーターからホーム上に降り立ったことに気づいたとき、駅係員がその利用客のところまで行って手助けをするならば、ホームからの転落を防ぐことができる。
そもそも、鉄道の利用客は必ず改札口を通る。改札口を通ろうとする利用客に対し、改札口の係員が声かけをして、ホームまでの誘導をするならば、ホームからの転落を防げるだけではなく、到着した電車の中まで誘導することができる。
このように、改札口やホーム上に駅係員が配置されていて、声かけと誘導をするならば、視覚障害者は安全に電車に乗ることができるのである。駅係員の配置を徹底することを、視覚障害者や視覚障害者団体は願っており、定期的に要望をしているが、合理化を図ろうとする鉄道会社は、その要望をなかなか聞き入れようとはしない。それは、無人化駅が増えつつあることからも明らかである。
(6)電車到着時に駅ホーム上に流れる音の充実:
おそらくはどの駅ホームにおいても、電車が通過したり到着したりすることを知らせるためにアナウンスや音が流れているはずである。しかし、そのアナウンスや音は統一されておらず、駅舎によってまちまちである。
「まもなく電車が参ります」というアナウンスが流れたとき、その電車が通過するのか、駅に止まるのかはまったく判らない。「まもなく電車が通過します」とか「まもなく電車が到着します」とか、利用客にはっきりと判るようにアナウンスが流れる駅舎は極めて少ない。したがって、電光掲示板を見ることができない視覚障害者には、通過なのか止まるのかは、電車が来るまで判らないのである。
電車が到着したことは、モーター音等で判るが、電車のドアが開いたのかどうかは判らないことがある。古い車両の場合はドアが開くときに比較的大きな音がするので判るが、新しい車両の場合にはドアが開く音がほとんどしないのでいつドアが開いたのか判らない。この間、視覚障害者は普段よりも耳に神経を集中しており、大変な緊張状態にある。
さらには、「電車が到着します」などというアナウンスが流れて30秒ほども経って電車が入ってくることがある。わずか30秒と思う人がいるかも知れないが、視覚障害者にとってはずっと耳に神経を集中させているので、非常に神経が疲れる。その間の視覚障害者とりわけ全盲者の緊張状態は筆舌に尽くしがたいものがある。その緊張状態の中で、電車のドアが開く音を聞き取るにはさらに緊張が高まる。したがって、いつ電車が到着したのか、いつドアが開いたのかを、視覚障害者が簡単に把握することができるような方式が必要である。
いつ電車がホームに到着したのか、いつドアが開いたのかを、視覚障害者が簡単に把握することができる方式をとっているところがある。それは大阪のJR環状線のすべての駅ホームにおいてである。
環状線の駅ホームでは、電車の到着を知らせるアナウンスに続いて、メロディーが流れ出す。そして、そのメロディーが止まると同時に電車のドアが開くのである。この方式だと、メロディーが鳴り続けている間はホームに電車が入りつつあることが判り、メロディーが止まると電車のドアが開いたことが判るのである。この方式を採用している駅ホームにいる視覚障害者は、電車がどんなに新しい車両で音が静かであっても、ドアの開く音がまったく聞こえなくても、電車の到着とドアが開いたことが簡単に把握できるのである。
私が電車に乗るのは、図書館や会議に行くときや、仕事やカラオケボックスに行くときぐらいである。つまり、毎日のように外出はしているが、いつも乗る電車は同じものなのである。したがって、すべての駅ホームの状況を知っている訳ではないが、私鉄にしても地下鉄にしても、JR環状線と同じ方式をとっている駅ホームはない。
このJR環状線が、視覚障害者の安全確保のためにこの方式をとっているのかどうかについては判らないが、駅ホームに流れるメロディーの「停止」と到着した電車のドアの「開き」とを連動させる仕組みのこの方式は、駅ホームに可動式ホーム柵が設置されていないホームにおいては、視覚障害者の駅ホームからの転落を防ぐには有効なものであることは多言を要しない。したがって、視覚障害者の単独での「移動の自由」を保障するためにも、ほかのすべての駅ホームでもこの方式をとったならば、視覚障害者は単独で鉄道を利用するときに、筆舌に尽くしがたいような緊張を強いられることはなくなることになる。
(7)無人駅における安全確保のための仕組みづくり:
「無人駅」とは、駅舎の切符売り場にも改札口にもホーム上にも駅の係員がまったくいない駅のことである。全国には5千以上の駅があるそうだが、そのうちの3割程度が無人化されているそうである。そのような駅の無人化はどんどん進んでいる。
無人化駅を障害者が利用するのは困難を来すことがある。手助けを願ってもすぐの対応はない。改札機にトラブルが生じたとき、改札口を通れないことになる。
鉄道会社の言い分は、「事前に連絡をしていただければ、その駅に係員を派遣します」とか「トラブルが生じたときに連絡をいただければ、隣の駅から係員をすぐに向かわせます」等々である。「事前の連絡」というが、障害者は常に計画通りに行動しなければならないとの前提に立った言い分である。
障害者は外出に際してヘルパーの支援を求めることがあるので、日程調整の関係から計画を立ててさまざまな予定を組んでいることが多い。しかし、「予定は未定」という言葉があるように、計画通りに事が進まないことがある。緊急の外出に際しては、利用駅に事前の予約が困難なことがあるのは多言を要しない。それにもかかわらず、障害者の利用に当たっては「事前予約」が強調されるのである。
視覚障害者の場合には、無人化駅でトラブルが生じたときに連絡しようとしても、緊急連絡装置がどこにあるのかが判らない。そのために、改札口を通れなくなる。こんなとき私は、仕方がないので、ゲートを足で押して改札口を無理に通ることがある。
駅の無人化に反対する障害者の声は高まっている。しかし、駅の無人化は止まることはなく、全国に広がっている。障害者の中には、駅の無人化は障害者の社会参加を阻害する人権侵害だとして裁判を起こしている者もいる。
駅の無人化は、障害者の「移動の自由」を妨げる以外の何ものでもないのであるから、視覚障害者の単独での「移動の自由」を保障するためにも、駅の無人化をやめるか、または、無人駅における障害者の安全確保とスムーズな利用のための仕組みづくりを急ぐ必要がある。
(8)自動車の接近を察知させるための設備の搭載と充実:
大都市では、どこに行っても自動車で溢れている。自動車が増えれば増えるほど、自動車事故はそれに比例して増える。そして、その事故に視覚障害者が巻き込まれることもある。
最近の自動車は、ハイブリッド車のようにエンジン音が小さくなっている。電気自動車にいたっては、モーター音と、タイヤが地面をこする摩擦音が微かにするだけである。すなわち、自動車の接近を知らせるエンジン音等が小さいということは、視覚障害者の単独歩行において、安全確保をすることが極めて困難な状態だということである。
自動車には、接近を知らせるためのさまざまな装置が搭載されている。右折や左折やバックすることを知らせるための声や音の装置がそれである。しかし、せっかく搭載されている装置の電源を運転手等が切っていることもある。バックを知らせる音の装置を切っていたトラックに、盲導犬がはねられて死んだという事故も起きている。
さまざまな音が溢れている町中を単独歩行する視覚障害者は、耳に神経を集中させながら歩いている。しかし、いくら耳に神経を集中させて、自動車の接近に注意を払おうとしても、自動車から発せられるエンジン音等が小さければ、それを察知することは困難になる。困難になればなるほど、自動車事故に遭う危険性が高くなることは誰にでも判るはずである。
したがって、視覚障害者の単独での「移動の自由」を保障するためには、自動車の接近を知らせる音が必ず出るようにして、その音によって視覚障害者が自動車の接近を察知することができるようにする必要がある。こんなことは誰にでも判るはずであるにもかかわらず、実際に音の出る設備が作動しないようにスイッチを切っていることがあるのである。自動車事故は他人事ではないと考えるべきである。
(9)盲導犬に対する理解の向上を図るための啓発等の充実:
道路交通法では、町中を移動するに当たって視覚障害者は白色または黄色の杖を携えるか、盲導犬を連れていなければならないと規定されている。
白い杖(白杖)を持って歩いている人を見かけたら、自動車を運転している者は、一時停止するか徐行するかしなければならない。しかし、黄色の杖を持っている人を見かけた場合に、徐行等をするような運転手はいるだろうか。白杖は「目の見えない人が持っているもの」との認識はあっても、黄色の杖を持っている人も「目が見えない」と知っているだろうか。学校での人権教育等において、白杖についての話はするが、黄色の杖について話をするだろうか。現実に黄色い杖を持って歩いている人に出会うことはまったくないといっても過言ではない。
念の為に一言すると、雪が降る地域では、視覚障害者は白杖よりも黄色の杖を持って歩くほうがよい。なぜなら、雪の中では白杖はほとんど目立たないからである。雪が降っていたり積もっていたりする地域に住んでいる視覚障害者は、自動車事故に遭わないためにも黄色の杖を持って歩くべきだと私は考えている。そして、自動車運転免許を取得するための講習所において、白杖についての教育だけではなく、黄色の杖についても教育を為すべきである。
前述したように、道路交通法では、視覚障害者は白杖等を持つか、盲導犬をつれて歩くことが義務づけられている。盲導犬を連れていることによって、それを連れている人は「目が見えない人」だということが周辺の者には判るので、手助けの声かけがなされることにもなる。
盲導犬と一緒に歩けば、基本的には、町中を安全に歩くことができる。その点では極めて有用である。しかし、飲食店やホテル等を利用しようとするときに、利用を拒否されることが未だにある。それは、この欄の前回の「愼英弘の部屋13」の冒頭でも述べた通りである。
盲導犬に対する社会の人々の理解の向上を図るために、学校での教育や市民向けの啓発に力が注がれてはいるが、現実にはなかなか理解が進んでいない状況が見受けられる。
したがって、これまで以上にいっそうの啓発の充実が図られなければならない。
(10)視覚障害者に対する社会の人々の意識を高めるための啓発等の充実:
私の経験するところでは、この半世紀の間に、視覚障害者に対する社会の人々の意識は大きく変わったと感じる。単独歩行をしていて、かつては嫌がらせを受けたり、いたずらをされたりしたが、ここ20年ぐらいはそのようなことをされた経験はない。このような状況になったのは、学校における人権教育の成果であり、市民向けの啓発活動の結果だといえる。
単独歩行をしている視覚障害者に対する社会の人々の多くは、支援のための声かけをしたり、さりげなく手助けをしたりするようになってきている。
しかし、社会の人々みんながみんな、このように接してくれている訳ではない。道を歩いていて、肩が触れたといっていちゃもんをつけられる経験を3度したことがある。ほかに、嫌がらせではないが、まったく見知らぬ人から「お金を貸してほしい」と言われたことがある。「いつ返してくれるのか」と言うと、「ああ、千円カンパをしてほしい」と言い直してきた。断ることは可能であるが、走って逃げることができない視覚障害者にとっては、付きまとわれたら困るので、いやいやながらカンパせざるを得ない経験も最近している。
とはいえ、このようないやな経験はそんなに多くはない。ほとんどの社会の人々はたいへん親切に声かけをして手助けをしてくれる。視覚障害者の「移動の自由」を保障するためには、さまざまな安全確保のための設備の充実はもちろん必要であるが、社会の人々の声かけと手助けは欠かすことができない。
したがって、視覚障害者の単独歩行での「移動の自由」を保障するためには、社会の人々の意識をいっそう高めるための教育や啓発の充実が必要である。
おわりに
以上述べてきたことに取り組むならば、視覚障害者は、まさに「移動の自由」を手に入れることができる社会になるだろうと私は確信している。
最後になるが、私が書いた資料をこの後につけておく。
この資料は、1995年7月に、関西で活動していた視覚障害者から依頼されて作成したものである。依頼者は、視覚障害を有する者の鉄道利用において、安全確保のために鉄道会社との交渉で使いたいので、作ってほしいと私に言った。それを受けて作成したものであり、できあがった資料を同年8月に依頼者に渡した。それをどのように使ったのか、鉄道会社に提出したのかどうかについては知らされていないので、私には判らない。その人はすでに鬼籍に入っているので、今となっては確認のしようがない。
以下に掲載するものがその資料である。文章を書き加えたり削除したりせず、当時の文章のままである。
「鉄道利用障害者の安全確保のためのマニュアル」
ここに作成した資料は、鉄道(地下鉄を含む)を利用する障害者とりわけ視覚に障害をもつ「視覚障害者」や「盲ろう者」の安全確保をするためのものです。関係機関はここに掲げてある内容を実行し、配慮ある姿勢をとられることを要望する次第です。これが実現するならば、視覚に障害をもつ者の鉄道事故は格段に減少するものと確信しています。
1 改札口における配慮
-
白杖を持った者が改札を通ったときには、駅係員は必ず声をかける。
- 声のかけ方は「案内しましょうか」というように、相手の意志を確かめる方法で行う。
- 「イエス」の答えがあったときには、駅係員の肘などを持たせて誘導する。
- 「ノー」の返事があったときには、そのまま一人で行ってもらうが、安全確保のために念を入れるということで安全に電車に乗り込むことを確認する。
-
改札の出入口付近には必ず点字ブロックを敷設する。
- 改札の内側に誘導用点字ブロックが敷設されていることは多いが、改札の外側に敷設されていることは少ない。
2 ホーム上における配慮
-
ホームには必ず駅係員を配置する。
-
ホーム上で白杖を持った者を見かけたら、駅係員は「案内しましょうか」と声をかける。
- 「イエス」の答えがあったときには、目的の電車に乗せる。その際、予めどこの駅で降りるかを聞いておく。
- 乗せたときもし座席が空いているならば、座席に座らせ、ドアから何人目に座っているかを伝える。
- 乗せて電車が発車した後、その人が降りる駅に連絡をとり、到着駅での安全確保も行う。
- 「ノー」の答えがあったときには、そのまま放置しておくのではなく、ホーム上はたいへん危険であるので、電車に安全に乗ったことを確認するまでその人のそばを離れない。
- 「ノー」の答えがあったときにも、どこの駅で降りるかを予め聞いておき、電車が発車した後、到着駅に連絡し、安全の確保を行う。
-
ホーム上には点字ブロックが敷設されていることが多いが、点字ブロックは安全確保のためには万全でないことを充分に認識する必要がある。
- 危険を表す点ブロックとホームの表面に貼ってあるタイルとが、白杖や靴の裏で識別しにくいことがある。したがって、ホーム表面には点ブロックと紛らわしいようなタイルは貼らない。
- 危険を表す点ブロックはホームの端から端まで隙間なく敷設する。
- ホームで電車が止まらない位置には転落防止用の手すりを必ず設置する。
3 券売機
-
券売機の設置場所を知らせるための音声ガイドを行う設備を整える。
-
券売機には点字表示をする。
- 点字表示はボタンの上にあったり下にあったりすることがあるので、どちらかに統一する。
- 券売機はタッチパネル式は導入しない。
4 階段の手すりでの案内
-
コンコース階からホームに上がったり下りたりする階段の手すりには、そのホームがどこ行きの電車が止まるホームであるかを手すりに点字表示する。
-
ホームではその駅名をアナウンスしていないことがある。したがって、階段手すりにはその駅名も点字表示する。
5 トイレの位置案内
-
トイレには男女別の点字表示プレートを取り付ける。
-
白杖を持った者がトイレを駅係員に尋ねたときには、快くトイレまで案内する。
6 市民への啓発
-
改札やホームに白杖を持った者がいたときには、気軽に声をかけるように市民(とりわけ鉄道を利用している人)にPRする。
-
駅係員がホームにいたとしても、一人では多数の利用者の安全確保には充分ではない。したがって、障害者の安全を確保するためには、市民の協力が必要であることを認識し、PR活動に力を入れる。
※白杖を持った者への声かけは、一般的には音声で行うが、「盲ろう者」には音声では伝わらないことがあるので、手話で伝えたり、掌に文字を書くという手段を使う必要がある。このことは十二分に認識し、鉄道関係者に徹底させる。
「共に築く共生社会の実現へ」パネルディスカッション開催
Contact
お問合せ
障がい者の文化芸術活動及び鑑賞に関するご相談・
事業・ホームページ・情報紙に関するお問合せ
072-290-0962
受付時間:平日 10:00~18:00